「ピアノを始めたいけれど、楽譜も読めないし、何から始めればいいのか分からない」——そんな不安を感じていませんか?
『30日でマスターするピアノ教本』は、楽譜が読めなくても、指が動かなくても大丈夫なように作られた初心者向け教材です。
とはいえ、「どうやって進めるのが正解?」「続けられるかな…」と迷うこともありますよね。
この記事では、教材の使い方や効果的な進め方、つまずきにくい練習スケジュールまで初心者の目線で分かりやすく解説しています。
「ピアノのことは全然分からないけど、とにかく始めてみたい!」という方にこそ、ぜひ読んでいただきたい内容です。

この記事では、教材の使い方や挫折しないコツを具体的にまとめていますが、「そもそもこの教材って、どんな内容?」「自分に合ってるのかな?」という方は、先に『30日でマスターするピアノ教本』完全ガイドもチェックしてみてください。
『30日でマスターするピアノ教本』を効果的に使うには?
教材を手にしたものの、「どうやって進めればいいんだろう?」「自分にも本当に弾けるようになるのかな…」と、不安を感じている方も多いかと思います。
そんな方にこそ知っておいてほしいのが、この教材の“サポート力”です。
『30日でマスターするピアノ教本』は、初心者でも無理なく上達できるよう、動画・テキスト・楽譜が連携してしっかり支えてくれます。
とはいえ、やみくもに取り組むだけでは「どこまで進めればいいか分からない」「弾けない部分でつまずく」といった壁にぶつかってしまうことも。
このセクションでは、そんな不安を解消しながら教材を最大限に活用できるよう、「効果的な進め方」と「つまずきにくい工夫」を具体的に解説していきます。
1日30分でOK!基本の進め方とスケジュール
『30日でマスターするピアノ教本』は、1レッスンあたり約10〜20分で構成されており、忙しい人でも取り組みやすいのが特徴です。
基本のスケジュールとしては、次のような進め方がおすすめです。
| 曜日 | 学習内容 |
|---|---|
| 平日(月〜金) | 1日1レッスン進める(動画視聴+練習)例:月曜=レッスン1、火曜=レッスン2… |
| 土日 | 1週間の復習+苦手な部分を重点的に練習必要に応じて録音や通し練習も◎ |
このサイクルで1週間に5レッスン進めれば、約6週間(=1.5ヶ月)で1巻を完了できます。

第1弾は難易度が易しいので、この予定よりも早く進められますよ。
「毎日できない」という方は、1レッスンを2日に分けて進めるスタイルでもOK。
重要なのは“完全に止まらないこと”です。
特に初心者の方は、「今日はDVDだけ見る」「手元の動きだけ真似する」という日があっても構いません。
続けることが最大の上達法です。
「弾けない」を乗り越える!挫折しない工夫
最初はうまくいかないのが当たり前です。
「指が思うように動かない」「両手になると弾けなくなる」など、途中でつまずいてしまうのは自然なこと。
大切なのは、その時どう乗り越えるかです。
おすすめの方法は、「真似する」→「分けて練習」→「合わせる」のステップです。
まずはDVDの手元映像をじっくり観察しながら、同じ動きになるように真似してみましょう。
次に、片手ずつ練習し、苦手な部分だけ繰り返します。

いきなり両手で弾こうとせず、「右手→左手→両手」の順番で練習すると、挫折しにくくなります。
また、録音や録画をして自分の演奏を見返すと、成長を実感でき、モチベーションの維持にも効果的です。
1週間前の演奏と比べてみて、「意外と弾けるようになってる!」と感じられたら、継続の自信につながりますよ。
動画・楽譜・テキストの最強活用術
教材には「DVD(または動画)」「ドレミ・指番号付きの楽譜」「140ページのテキスト」が付属しています。
それぞれの役割を正しく理解して使い分けることで、理解度と上達スピードが大きく変わります。
| アイテム | 内容・特徴 | 役割・使い方 |
|---|---|---|
| DVD(または動画) | 実際の演奏映像/手元の動きが正面・上から見える | 弾き方のイメージをつかむ/フォームや動きを視覚的に理解するためのツール |
| 楽譜 | 3段階構成(ドレミ付き → 指番号付き → 通常譜) | 徐々に譜読みの力を育てるステップ教材。段階を踏むことで初心者でも安心 |
| テキスト(140ページ) | ピアノの構え方、リズム、記号などの基礎知識 | 教科書的な位置づけ。演奏だけでなく、音楽の基本も学べる補助資料 |
たとえば、最初はDVDでざっくり流れを掴み→ドレミ付き楽譜で練習開始→慣れてきたら通常譜面に移行という順番が効果的。
また、わからない音楽用語が出てきたら、すぐにテキストで調べるクセをつけると理解が深まります。
教材は“見て・聴いて・弾いて・読んで”の4方向からサポートしてくれる構成です。
この4つをバランスよく使えば、初心者でも確実にステップアップできます。
教材の効果を引き出す5つの工夫
教材の使い方や練習の進め方がわかってくると、次に気になるのは「それをどうやって続けるか」ですよね。
『30日でマスターするピアノ教本』は、動画通りに進めれば弾けるようになるよう設計されていますが、それでも「続けられるか不安」「途中で飽きてしまいそう」という声はよく聞かれます。
そこでこの章では、教材の効果を最大限に引き出すためのちょっとした“工夫”を5つご紹介。
どれも難しいものではなく、今日からすぐに取り入れられる方法ばかりです。
毎日続けるコツは“時間の固定化”
継続の最大の敵は、「今日はやらなくていいか…」という気持ちです。
これを防ぐためには、“練習を習慣化”することが重要です。
おすすめは、毎日決まった時間に「ピアノに触る時間」を組み込むこと。
たとえば、
- 朝の支度前に10分だけ
- 夕食後のリラックスタイムに30分
- お風呂上がりに「1曲だけ練習」
など、自分の生活リズムの中で「ピアノが続きそうな時間帯」を見つけて、習慣化してみてください。
スケジュール帳やカレンダーに「ピアノ」と書くだけでも意識が変わります。
また、毎日でなくても「火・木・土はピアノの日」と決めておくだけで、三日坊主を防ぎやすくなりますよ。
弾けないときこそ「手本の真似」が近道
初心者が最も挫折しやすいのは、「何度やっても弾けない」「指がもつれる」という場面です。
でも、そこであきらめるのはもったいない!
そんなときは、理屈を考えるより「手本の真似」を徹底することが一番の近道です。
具体的には、DVDやオンライン動画の中で、海野先生の手の動きをじーっと観察してみてください。
手の高さ、指の角度、タイミング…「音」ではなく「動き」に注目するのがポイントです。
一度止めて、自分の手の動きを見比べてみましょう。
「こう動かしてたのか!」と気づく瞬間がきっとあるはずです。
また、映像は何度でも再生できます。
「右手だけ3回見る」「この部分だけ10回繰り返す」など、自分に必要なだけ“真似し倒す”ことで、徐々に弾けるようになっていきます。

実は私自身も、最初は「全然弾けない…」「何が間違ってるのか分からない」と悩んでいました。
でも、何も考えずに“とにかく手本の動きを真似する”ことを繰り返すうちに、少しずつ指が動くようになってきたんです。
この経験から、「初心者にとって“真似する”ことは最強の練習法だ」と強く感じています。
そのときの気づきや練習の様子は、別の記事で詳しく紹介していますので、よければ参考にしてみてください。
⇒初心者目線で書いた『30日でマスターするピアノ教本』の体験レビューと「真似練習」の効果
録音すると続けたくなる理由
練習の成果を目に見える形に残すことは、モチベーション維持に非常に効果的です。
特におすすめなのが、「自分の演奏を録音・録画してみる」こと。
最初は「恥ずかしい…」「思ったより下手かも…」と感じるかもしれません。
でも、1週間・2週間と続けていくと、以前の演奏との違いがはっきり分かるようになります。
「少しだけど、確実に成長してる」と実感できることが、最大のやる気につながるのです。
録音・録画といっても、スマホ1台あれば十分。自分しか見ないので、気楽に試してみてください。
上達を記録するという意味では、練習ノートに日付と練習内容を書くだけでも効果的。
自分の変化を「見える化」することで、継続の原動力が生まれます。
練習環境を整えるだけで集中力アップ
ピアノの練習効率は、環境で大きく左右されます。
ちょっとした工夫だけで、集中力が続きやすくなったり、弾き間違いが減ったりすることもあります。
たとえば、
- ピアノやキーボードは出しっぱなしにする
- 楽譜スタンドは目線の高さに合わせる
- スマホやDVDプレーヤーは手元に置いて、すぐ再生できるようにする
こういった物理的な手間を減らすことで、「練習に取りかかるまでの心理的ハードル」がぐっと下がります。
また、照明の位置や音量も意外と重要。暗い場所や音が小さすぎる環境では、集中力が落ちてしまいます。
自分の“ピアノスペース”を作るイメージで、ちょっとだけ整えてあげると、毎日の練習がぐっと快適になりますよ。
進歩を“見える化”しよう
最後の工夫は「成功体験を記録する」ことです。
特に初心者のうちは、小さな“できた!”を見逃さないことが上達のカギになります。
たとえば、
「初めて両手で弾けた!」
「指番号を見ずに1曲弾けた」
「リズムがスムーズに取れた」
そんな小さな進歩をYouTubeに記録したり、XやインスタなどのSNSでつぶやいたりしてみてください。
人に言うのが恥ずかしい方は、スマホのメモや日記アプリでもOK。
「ちゃんと積み上がってる」という実感があるだけで、「もうちょっと続けてみようかな」と前向きな気持ちになれます。
“できなかったこと”より“できたこと”に注目する習慣を持つことが、ピアノの上達にはとても大切です。
練習が楽しくなる!よくある悩みと対策Q&A
教材の使い方や続けるための工夫がわかっても、実際に取り組み始めると「今日はやる気が出ない…」「うまく弾けなくて落ち込む…」といった壁にぶつかることもあると思います。
でも、そうした悩みはあなただけのものではありません。みんな同じようにつまずいたり、試行錯誤したりしながら練習を続けています。
ここでは、そうした「よくある悩み」とその対策をQ&A形式でわかりやすくご紹介。
もし今、気持ちが揺れていたり不安を感じているなら、少しでもヒントになれば嬉しいです。
毎日練習しないとダメ?
A:いいえ、大丈夫です!大切なのは“続け方”の工夫です。
『30日でマスターするピアノ教本』は、毎日取り組むことを前提にしていません。
むしろ、忙しい人や高齢の方でも続けられるよう、「1日30分程度、週3〜4日でもOK」という設計です。
毎日やろうとすると、ちょっとサボっただけで「もうダメだ」と思ってしまいがち。
でも、週に3〜4回でもしっかり取り組めば、十分に上達できます。
おすすめは、「今日はやらない」のではなく「今日は映像だけ見る」「片手だけやってみる」といった“軽めの関わり”を続けること。
これだけで、“ゼロの日”を防ぐことができ、習慣が途切れにくくなります。
また、1日休んだあとに「じゃあ明日は15分だけやってみよう」と切り替える柔軟さも大切。
“毎日”にこだわりすぎず、長く続けることを優先しましょう。
1回の練習時間はどのくらいが理想?
A:1日30分を目安に、“集中できる時間”を優先しましょう。
教材自体は「1日10~20分で1レッスン」という設計になっているため、30分もあればじゅうぶんに練習できます。
むしろ、大切なのは時間の長さよりも「どれだけ集中できたか」。
たとえば、
- 最初の10分はDVDを見ながら動きを観察
- 次の10分で片手ずつ弾いてみる
- 最後の10分で両手合わせや録音チェック
このように、短時間でも目的をもって取り組めば、1時間やるよりも効果的な場合もあります。
また、「今日は調子がいいから1時間」「明日は忙しいから10分だけ」と、日によって練習時間を柔軟に変えるのもOKです。
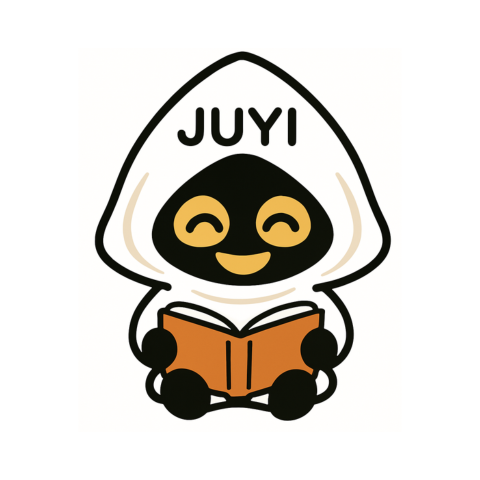
「時間」ではなく「濃度」を意識することで、疲れずに楽しく続けられるようになります。
途中で飽きたらどうすればいい?
A:思い切って“寄り道”するのもアリです!
ずっと同じ曲やレッスンばかりでは、誰だって飽きてしまいます。
そんなときは、一度立ち止まって「別の曲を弾いてみる」「指の練習曲で遊んでみる」など、“寄り道”をするのがオススメです。
『30日でマスターするピアノ教本』には、楽しく指を鍛える練習曲集が特典で付いています。
「チャルメラ」「チューリップ」「キラキラ星」など、どれも親しみやすく、気楽に楽しめる曲ばかり。
また、「今日は弾かずにピアノ系YouTubeを見る」「演奏会を観る」など、ピアノに間接的に触れる日を作るのも効果的。
“ピアノを嫌いにならない工夫”として、リフレッシュも練習の一部と考えてOKです。
結果的に「やっぱり弾きたいな」と思えたら、それが一番のモチベーション回復につながります。
まとめ|“自分のペース”こそ上達のコツ
『30日でマスターするピアノ教本』は、「初心者でも名曲を弾けるようになる」という夢を、少しずつ現実に近づけてくれる教材です。
この教材を活かすために、ぜひ以下の3つのポイントを意識してみてください。
- 動画・楽譜・テキストを役割ごとに使い分けること
- 無理のないペースで続けること
- 上手くいかなくても、「真似する」ことから始めること
これらを心がけるだけで、練習がぐっと楽になります。
途中でつまずいたり、飽きたりすることもあるかもしれませんが、それは誰にでもある“上達の過程”。
今日はDVDを見るだけ、少し手を動かすだけでもOKです。
大人のピアノは、スピードよりも“楽しさ”が何より大切。
あなたのペースで、あなたらしくピアノを楽しんでください。
この教材が「ピアノって楽しい!」と思えるきっかけになりますように。

「他の人はどんな風に取り組んでるの?」と気になる方は、実際に使った人の口コミや評判をまとめた記事もあるので、ぜひ参考にしてみてください。
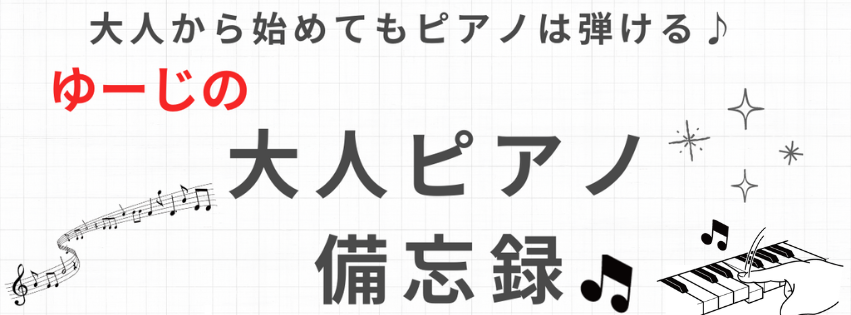
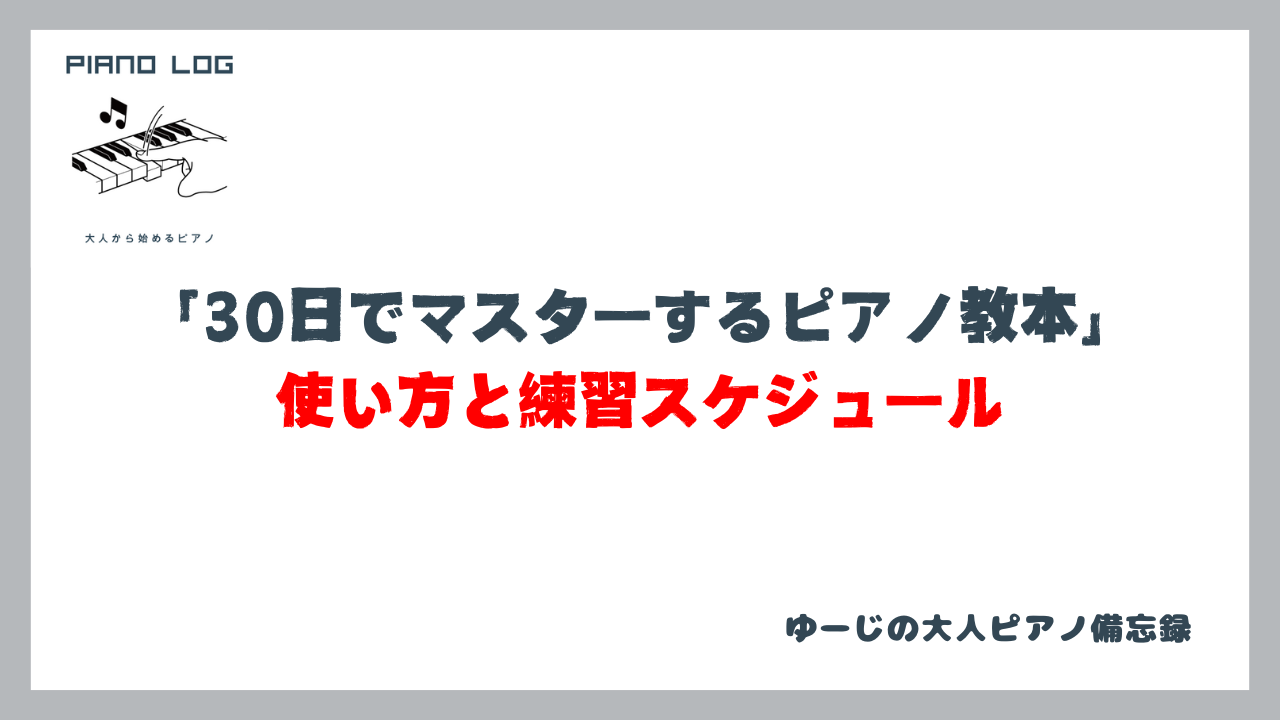
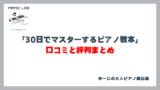


コメント