「別れの曲」と聞くと、どこか切なくて美しい旋律を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。
ピアノ初心者の私も「ゆっくりだし、音数も少ないから意外と弾けるかも?」と、最初は軽い気持ちでこの曲に挑戦しました。
しかし、実際にレッスンに取り組んでみると、その印象は一変。
アウフタクトや左右非対称のリズム、繊細な強弱表現、空白の「間」を感じ取るタイミング——どれも想像以上に難しく、「簡単そうに聞こえる曲ほど奥が深い」という事実を思い知らされました。
この記事では、「30日でマスターするピアノ教本」第2弾に収録されている《別れの曲(ショパン)》を練習して感じた、初心者ならではの苦戦ポイントや気づきを、リアルな体験として綴っています。
これからこの曲に挑戦する方や、初心者の視点でクラシックの世界を覗いてみたい方の参考になれば幸いです。
ゆっくりなのに難しい?ピアノ初心者が感じた「別れの曲」の壁
「別れの曲」といえば、美しくも切ない旋律が印象的なショパンの名曲。
テンポも比較的ゆっくりで、「これなら初心者でも取り組めそう」と思ってしまいそうですが……いざ弾いてみると、まったくの別世界でした。
私が「30日でマスターするピアノ教本」の第2弾でこの曲に出会ったとき、最初に感じたのは「思ったよりずっと難しい」という戸惑いです。
とくに、ただ指を動かせばいいという段階から一歩踏み込んで、「表現する」ことが求められる構成に圧倒されました。
左右の手でまったく異なるリズムを奏でたり、ほんの一音一音に感情が宿るような表現が必要だったりと、「ゆっくり=簡単」という先入観は一瞬で打ち砕かれたのです。
ここでは、実際に私が感じた「見るのとやるのは大違いだった!」というポイントを2つご紹介します。
リズムが違う左右の手|見てるだけじゃ分からなかった難しさ
まず最初につまずいたのは、左右で異なるリズムを同時に演奏するという点でした。
この曲は出だしからいきなりアウフタクトで始まります。つまり、拍の「頭」ではなく「前倒し」で音が出るんですね。
楽譜を見た段階では「ふむふむ、ここで始まるのか」と分かった気になっていましたが、実際に弾いてみるとタイミングがとにかくつかみにくい。
しかも、右手はメロディラインを、左手は伴奏のような役割を担っているのですが、まったく同じリズムで動くわけではありません。
右手が旋律を語っている間、左手は淡々と、でも正確に和音を刻んでいく必要があります。
片手ずつなら何とか弾けるのに、両手を合わせた瞬間にテンポが崩壊。
脳内で「こっちはこのリズム、でもこっちは…」と混乱してしまい、「これが初心者にとって最大の壁かも」と感じました。
一つひとつの音が“感情”を問われるような構成だった
この曲に取り組んでいくうちに、少しずつ分かってきたのは「ただ音を出せばいいわけじゃない」ということでした。
1小節に音が数個しかない場面も多く、そこでは「次の音までの間」をどう取るか、どんな風に“待つか”がとても大事。でも、その「間」が難しい。気持ちが先走って早く弾いてしまったり、逆に間延びしてしまったり…。
たとえば、1つの音をゆっくり弾いて「スッ…」と手を引くとき、「いまの音、ちゃんと気持ちが乗ってたかな」と、自分でもよく分からない不安にかられることもありました。
音が少ないぶん、ごまかしがきかないんですよね。
このとき初めて、「ピアノって“表現”なんだな」と思いました。
言葉がない代わりに、音に“気持ち”を込めなければ伝わらない。
そんな当たり前のことを、実感として味わった初めてのレッスンだった気がします。
クレッシェンドってこんなに難しい!?強弱表現との初対面
ピアノを始めてしばらくの間、「楽譜どおりに弾けたらOK」と思っていました。
ところが《別れの曲》に入った途端、「クレッシェンド」という魔物が現れます。
「だんだん強く」と書いてある通りに弾こうとするのですが、これがまぁ難しい。
頭では理解しているのに、体が全然ついてこないんです。
小さく始めて大きくなる?そんなにうまくいかない…
クレッシェンドは「だんだん強く」という指示。
最初は「ちょっとずつ音を強くしていけばいいのかな?」と、軽い気持ちでトライしました。
ところが、いざ弾いてみると……1音目でいきなり強すぎる。次で弱くなってしまう。3音目で焦ってまた強くして、4音目で勢い余ってガツン!
結果、「波打つような音量変化」ができあがりました(正しくは“なだらかな山”のはずなのに…)。
気持ちとしては「盛り上がっていきたい!」のですが、指が焦って先に突っ込んでしまう感覚。
まるで、坂道を転がる前にジャンプしてしまったような……。
しかも、小さく始めようと思うあまり、最初の音がかすれてしまうこともありました。
「だんだん大きく」の“だんだん”って、こんなに難しいんですね。
ただ鍵盤を強く押すだけでは強弱にならないと知った
もう一つ、初心者として大きな気づきだったのが、「強く押せば強い音になる」という単純な話ではなかったことです。
たしかに勢いよく鍵盤を叩けば大きな音は出ます。
でも、そうすると音色がガチャン!と割れてしまったり、曲の雰囲気が壊れてしまったり……。
たとえば、「優しく、でもだんだん情熱を込めていく」ようなフレーズで、単に“力任せ”に押しただけでは、まるで怒っているような音になってしまいました。
頭ではイメージできているのに、指がそのニュアンスを表現してくれないのです。
ちょっとだけ強く、ちょっとだけやさしく。
その“ちょっと”をコントロールするのが、こんなにも繊細な作業だとは思いませんでした。
こうして私は、初めて「音の強さ=感情の深さ」ということに触れた気がします。
そして同時に、「ピアノの表現力って、こういうことか…」と、ほんの入り口を覗いたような気持ちになりました。
テンポが遅いからこそ求められる“深さ”があった
ピアノを始めた頃は、「テンポが遅い曲のほうが簡単だろう」と思い込んでいました。
でも、《別れの曲》を弾いて、その考えは見事にひっくり返されました。
ゆっくりだからこそ、ごまかしがきかない。
間延びしないように気を張り続けないと、音楽として成り立たない。
“シンプル”ではなく“奥深い”という言葉のほうがぴったりだと感じました。
「ゆっくり=簡単」じゃない。むしろ緊張感がずっと続く
この曲のテンポは、決して速くありません。
だから最初は「これなら落ち着いて弾けそう」と安心していたのですが、実際には“ゆっくり進むぶん、ずっと緊張している”ような感覚でした。
速い曲なら、たとえ少し音を外しても、勢いで流れていってしまうことがあります。
でもこの曲では、一音一音に“間”があり、その“間”があるからこそ、音の重みやニュアンスが問われるのです。
「次の音までどう“待つ”か」「空白の中でどう“雰囲気を保つ”か」――
演奏中、そうした“見えないこと”に意識を向け続けるのは、思った以上に体力も集中力も使いました。
テンポが遅いというのは表現力をごまかせないということでもある。
だからこそ、初心者の私にとっては、ものすごく勉強になる一曲だったと思います。
まとめ|別れの曲で感じた“ピアノの表現力”との出会い
《別れの曲》は、テンポも速くないし、音の数も多くない。
でも、それなのに――いや、それだからこそ、難しかったです。
アウフタクトや異なる手のリズム、繊細なクレッシェンド、余白の“間”の取り方……
どれも「楽譜に書かれていること」以上に、「感じること」が求められました。
ピアノって、ただ音を鳴らすだけじゃない。
どう鳴らすか、どんな気持ちを込めるか、それを“音に変える”ための技術と感性が必要なんだ――そう気づかせてくれたのが、この曲でした。
演奏を終えた今、完璧に弾けたとは言えません。
でも、「表現するってこういうことなんだ」と思える体験ができたことは、何よりの収穫でした。
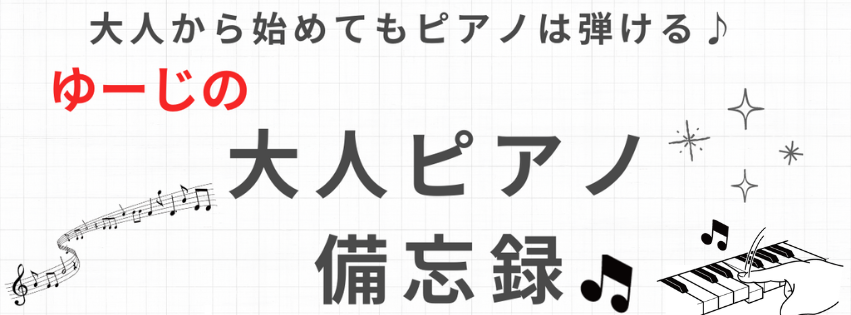
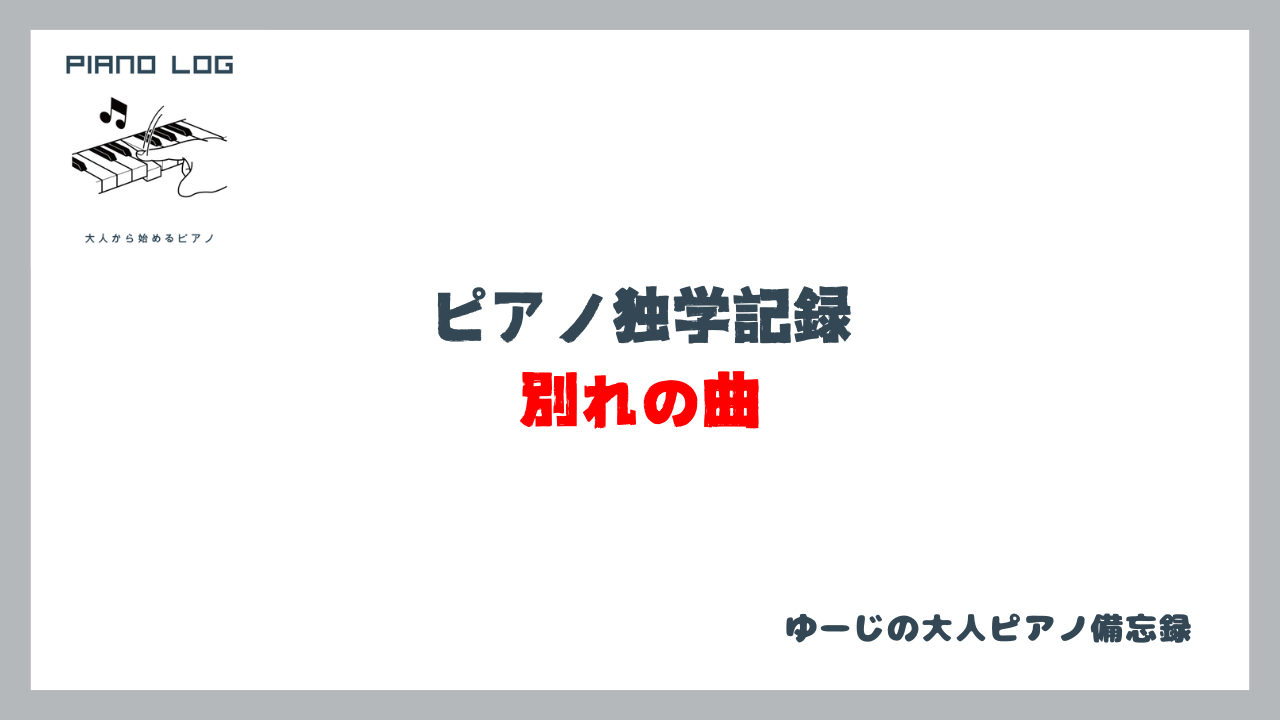


コメント