ピアノ初心者の私「ゆーじ」が、『30日でマスターするピアノ教本&DVD』を使って練習を始めて約2か月。
今回は、コブクロの名曲「蕾」に挑戦しました。
クラシック曲とは異なる複雑なメロディラインや独特のリズム感、新しく登場したスラーやブレス記号など、これまでとはひと味違う課題が盛りだくさん。
さらに、楽譜のドレミ表記が小さくなり、自力で音を読む練習も本格化しました。
前回までの練習で身につけた基礎力を土台にしつつ、1.5倍の長さになった楽譜を最後まで弾き切る集中力と記憶力も試される1曲。
成長と課題がはっきり見えた今回の練習記録を、動画とあわせてお届けします。
クラシックとはひと味違うポップス曲「蕾」に挑戦して感じたこと
ポップス曲の「蕾」は、これまでのクラシック曲とは少し違い、メロディラインがより複雑になっていました。
私自身、最終的な目標としてケツメイシの「さくら」を弾くことを考えているので、この曲は良いステップアップの練習になると感じました。
クラシックに比べて、音の並び方やリズムの取り方に歌心が求められ、ただ正しい音を並べるだけでは足りません。
耳で覚えているメロディを指で再現するために、フレーズの抑揚や音の切り方を意識しながら練習を進めていきました。
メロディラインが複雑で目標曲へのステップアップにぴったり
「蕾」はクラシック曲のように規則的で分かりやすいメロディではなく、音の動きがより細かく、跳躍や装飾的な動きも多く含まれています。
この複雑さが、次の目標であるケツメイシの「さくら」に向けた良い練習になっていると実感しました。
単に譜面を追うだけではなく、耳でメロディの流れをつかみ、指先でそのニュアンスを表現することが必要になります。
今までよりも曲全体を立体的にとらえながら弾く感覚が求められ、練習していて自然と集中力が高まっていきました。
クラシックとは違うリズム感や歌心を意識する練習
「蕾」では、クラシック曲のような均等で安定したリズムではなく、ポップスならではの揺れや間(ま)が重要になります。
一定のテンポを守りながらも、歌詞があるかのようにフレーズを“歌わせる”意識が求められました。
特にスラーやブレス記号が加わることで、フレーズのつなぎ目や音の切り方に自然な流れを作る練習になります。
この表現力の部分は、単なる音の長さや強弱だけでなく、「ここで息を吸うように音を軽くする」といった感覚的な工夫が必要で、最初は慣れない部分もありました。
しかし、この感覚をつかむことで、次第に“演奏”が“音楽”へと変わっていく実感がありました。
新しく出てきたスラーやブレス記号で表現力アップ
「蕾」の練習では、これまでの課題曲にはなかったスラーやブレス記号が初登場しました。
どちらも演奏に表情を与える大切な記号ですが、初心者にとっては「どうやって反映させればいいのか」がすぐには掴みにくい部分です。
スラーは音をなめらかにつなぐための記号、ブレスは歌うときのように息継ぎをするタイミングを示す記号。
これらを楽譜から読み取り、自然な演奏に落とし込むのは、ただ鍵盤を押すだけの練習とは一味違った難しさがあります。
しかし、この記号を意識できるようになると、曲の流れやニュアンスが一気に豊かになる。
次では、実際に私がスラーやブレスをどう感じ、どのように練習に取り入れたのかを具体的にお話しします。
「つなぐ」「息を抜く」のタイミングを楽譜から読み取る難しさ
スラーやブレス記号は、見慣れないうちは「ただのマーク」に見えてしまいがちです。
しかし実際に演奏しようとすると、「ここからここまでをなめらかに?」「この位置で息を抜くように間を取る?」と、楽譜を読むだけではイメージしにくいことも多くありました。
特に「蕾」はメロディラインが複雑で、クラシック曲のように拍の取り方が単純ではありません。スラーを意識してつなげたつもりでも、次の音への移動や左手の伴奏とのタイミングがずれてしまい、「思ったような流れにならない…」ということも。
ブレスも、ただ休符で止まるのとは違い、“音楽を呼吸させる”感覚が必要で、慣れるまでは難しさを感じました。
こうした「読む→理解する→弾く」のステップが、表現力を高める上で避けられない壁だと実感しました。
記号を意識すると曲の流れやニュアンスがぐっと変わる
苦戦しながらもスラーやブレスを取り入れて弾いてみると、曲の印象がまるで変わります。
スラーで音がなめらかにつながると、メロディ全体がひとつのまとまりになり、歌うような流れが生まれます。
逆にブレスを意識して“間”を取ると、そこで音楽が一度リセットされ、次のフレーズがより引き立つ感覚がありました。
これまでの課題曲では、音を正しく弾くことに集中していた私ですが、この曲では「どう弾くか」という意識が加わり、少しずつ演奏の楽しさが広がっていくのを感じました。
記号を理解し、表現として反映させることは、技術面だけでなく音楽全体の雰囲気作りにも直結する――そんな気づきを得られた練習でした。
ドレミ表記が小さくなっても大丈夫 徐々に楽譜を自力読みへ
今回の「蕾」では、これまでの課題曲と比べて楽譜のドレミ表記が小さくなっていました。
最初は「え、見づらい…」と思いましたが、実はこれが教材側の意図的な工夫。視覚的なサポートを少しずつ減らすことで、自然と音符そのものを読む力を養うステップに入っていたのです。
完全に表記をなくすと一気にハードルが上がってしまいますが、この“ちょっと見えづらい”加減が絶妙で、無意識のうちに自分で音を確認しながら弾く練習になっていました。
次のH3では、この表記の工夫がどのように楽譜読みの力につながったのか、そして実際に演奏しながら感じた変化についてお伝えします。
H2:目立たない表記で自然に音符を読む力を育てる工夫
この曲では、ドレミの表記が小さく、色も控えめになっていました。最初は「見にくいな」と感じたものの、演奏を続けるうちに、それが逆に音符を読むきっかけになっていることに気づきました。
大きくはっきりと書かれたドレミに頼ってしまうと、視線が楽譜の上の記号だけに集中し、本来の音符を読む力が育ちません。
そこで教材では、サポートを少しだけ残しつつ、自然に音符を見る習慣をつけるための“目立たない表記”にしていたのです。まるで補助輪を外す前の段階のような絶妙な設定でした。
ドレミを見なくても弾ける感覚が少しずつ身についてきた
ドレミ表記が小さくなったことで、完全に目で追わなくても鍵盤の位置や指の感覚で音を探せるようになってきました。最初は音を外すこともありましたが、「ここはこの指、この形」というパターンが少しずつ身体に染み込んでいくのを実感。
特に同じフレーズを繰り返す部分では、途中からドレミを見ずに演奏できる瞬間が増えました。こうした“小さな自立”の積み重ねが、後の楽譜読みの自信につながっていくのだと思います。
楽譜の長さ1.5倍で集中力と記憶力が試される構成
「蕾」はこれまでの課題曲よりも楽譜がぐっと長く、全体で約1.5倍のボリュームになっていました。
ページをめくる必要こそありませんが、覚える音の数やフレーズのパターンが増えるため、集中力と記憶力が一度に試される構成です。
短い曲なら多少ミスをしても最後まで弾き切れますが、長い曲になると後半で集中が途切れやすくなります。さらに、前半で間違えると「次こそ」と意識しすぎて、その後の演奏にも影響が出がちです。
この課題曲は、ただ鍵盤を押さえるだけでなく、体力や精神面でのスタミナ配分を意識しながら弾く必要があり、まるで小さなマラソンのような感覚でした。
弾き切るための体力と集中力の配分が課題
楽譜が長くなると、最初から最後まで同じテンションで弾き続けるのは意外と大変。
序盤で力みすぎると中盤以降に疲れが出てきて、テンポや表現が崩れがちになります。特に「蕾」はゆったりしたテンポながらも、音の数や表現の幅が広く、油断すると指先や肩に余計な力が入ってしまうことも。
演奏全体を見据えて、どこで力を抜くか、どこで一気に盛り上げるかを考えながら弾くことが、最後まで安定して演奏するための鍵だと感じました。
部分練習と通し練習をうまく組み合わせて乗り切った
曲が長いと、最初から最後まで通しで練習するだけでは効率が悪く、ミスの修正も難しくなります。私はまず苦手なフレーズや指使いの難しい部分だけを繰り返し練習し、それが安定してから全体を通して弾くようにしました。
部分練習で体に動きを覚えさせ、通し練習で全体の流れを確認する。この2つをバランスよく組み合わせることで、最後まで集中を保ちつつ演奏できるようになったと思います。
まとめ|「蕾」で感じた成長と次の目標へのステップ
楽譜が長くなることで、体力・集中力・記憶力のすべてが求められるのを強く感じました。単純に「最後まで弾けるか」だけでなく、曲全体の流れや表現を維持し続けるための計画性も必要になります。
部分練習で精度を高め、通し練習で全体の一体感を作る——この積み重ねこそが、長い曲を最後まで心地よく弾き切るための大きなポイントだと実感しました。
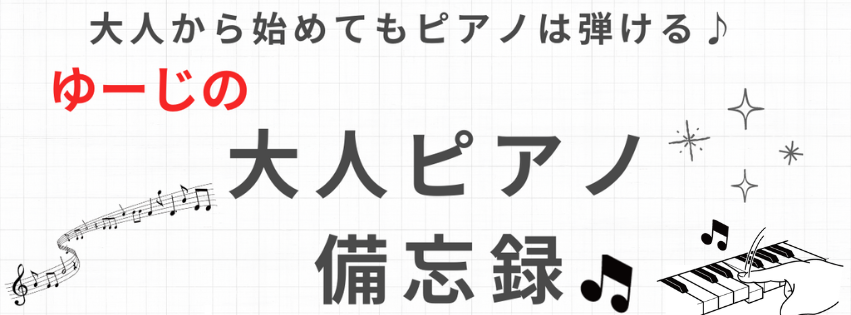
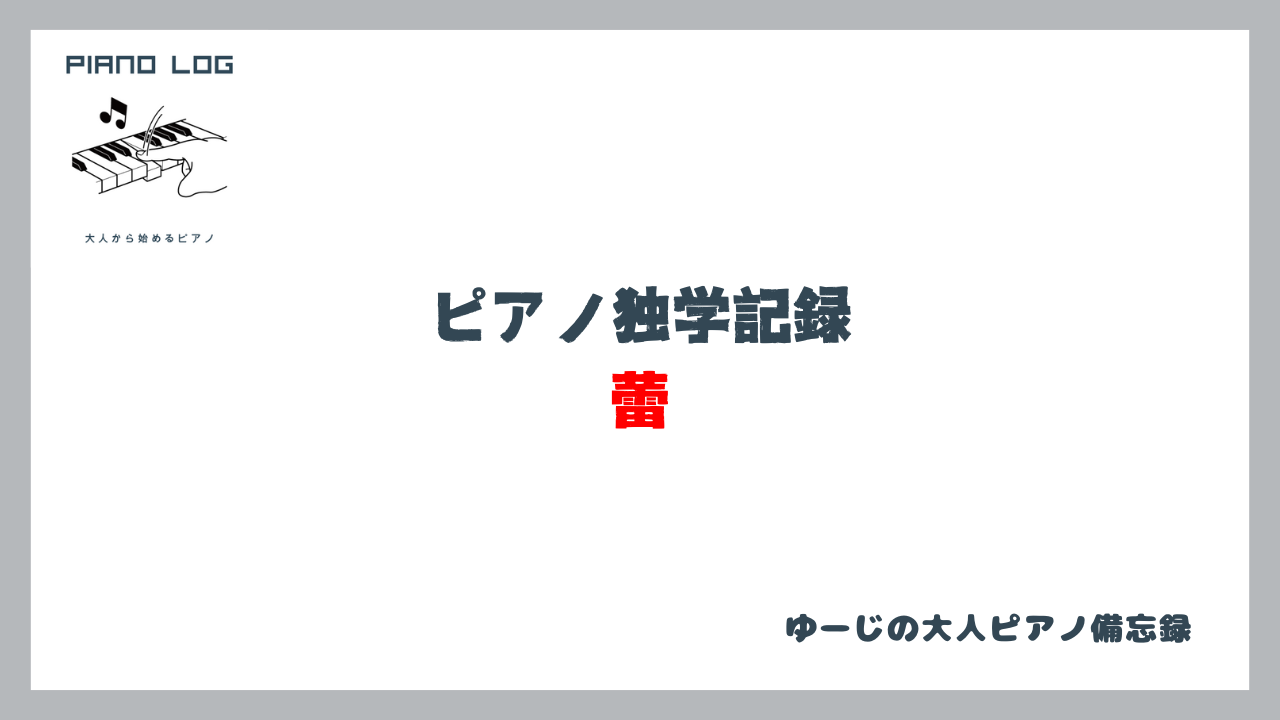


コメント