ピアノ初心者の私「ゆーじ」が、『30日でマスターするピアノ教本&DVD』を使って練習を始めて約2か月。
今回は、ドヴォルザークの『交響曲第9番「新世界より」第2楽章』のメロディとして知られる「遠き山に日は落ちて」に挑戦しました。
臨時記号が登場しますが、これまでの練習で身につけた基礎力で十分対応でき、自分の成長を実感できた内容でした。
一方で、情感をこめて弾く難しさや、同じ音の指使い表記が省かれることで楽譜を自力で読む力を試されるなど、新しい課題も盛りだくさん。
第3回レッスンの幕開けにふさわしいこの曲で、基礎力と表現力の両方に向き合った練習記録を、動画とあわせてお届けします。
臨時記号もクリア 自分の成長を感じられた一曲
第3回レッスンの1曲目「遠き山に日は落ちて」では、これまで避けられなかった臨時記号がいよいよ登場しました。
最初は少し身構えたものの、これまでの練習で培ってきた基礎のおかげで、思っていたほど難しく感じませんでした。
むしろ「あ、これなら弾ける!」という手応えがあり、少しずつではありますが確実に成長している自分を実感。
ピアノの練習は、毎日やっていると変化に気づきにくいものですが、こうして新しい要素に挑戦したときに、その積み重ねが形になって表れる瞬間があります。
このパートでは、臨時記号を乗り越えられた理由や、成長がもたらす練習へのモチベーションについて、私が感じたことを振り返ります。
これまでの練習で身につけた基礎が活きた瞬間
臨時記号が出てきたとき、以前の私なら「難しそう…」と身構えていたと思います。
しかし今回は、指の運びや音の位置感覚が自然と身についていたおかげで、そこまで混乱せずに弾き進めることができました。
特に、音の上下関係や鍵盤の距離感を身体が覚えていたことが大きく、楽譜を見ながらも余裕を持って指を動かせました。
このとき「今までの練習がちゃんと力になっているんだ」とはっきり実感できました。
成長を実感できると練習のモチベーションも上がる
弾けるようになった瞬間の喜びは、何よりのモチベーションになります。
特に今回は、臨時記号という新しい要素に挑戦しながらも「自分でもできる」という感覚を持てたことが大きな励みになりました。
練習はときに地道で単調に感じることもありますが、こうした成長の手応えがあると「次はもっと上手くなりたい」と前向きになれます。
この経験が、次の曲やさらに難しい課題へのチャレンジ意欲を強くしてくれました。
情感をこめる難しさと向き合う
ゆったりとしたテンポの曲ほど、弾き手の感情や音の表情がそのまま伝わります。
「遠き山に日は落ちて」もその一つで、ただ正しい音を並べるだけでは、曲が持つ深い情感や静かな美しさは表現しきれませんでした。
特にこの曲は、1音1音の間に漂う余韻や間の取り方が重要で、それを意識しながら弾くのは想像以上に難しいものでした。
演奏しながら気持ちを乗せるには、技術的な余裕と曲への理解が必要で、「感情表現の壁」に初めてしっかり向き合った瞬間でもあります。
次のH3では、この「深みを出す難しさ」と「余裕を持って弾くための工夫」について、もう少し具体的に振り返っていきます。
ただ弾くだけでは伝わらない“曲の深み”
「遠き山に日は落ちて」は、音符の数やリズム自体は決して難しくありません。
しかし、ただ楽譜通りに音を並べただけでは、この曲が持つ静けさや深い情景は聴き手に届かないと感じました。
特に、音と音の間にある“間”や、音が消える直前の余韻がもつニュアンスは、鍵盤を押す瞬間だけでなく、離す瞬間にも意識が必要です。
そうした細やかな部分を疎かにすると、曲全体が平坦に聞こえてしまい、「何か物足りない」という印象になります。
感情表現の余裕を持つために必要なこと
感情をこめる演奏には、まず「弾くことで精一杯」という状態を脱する必要があります。
私はこの曲で、指使いや音符読みで迷わないレベルまで繰り返し練習することで、ようやく表情をつける余裕が生まれました。
また、練習の中で曲の背景や情景をイメージすることも大切でした。
例えば「夕暮れの静けさ」や「一日の終わりに感じる安らぎ」を想像しながら弾くと、自然と音のタッチやペダルの使い方が変わります。
こうした余裕とイメージづくりの積み重ねが、感情表現の第一歩になると実感しました。
指使い表記が減っても困らない 楽譜慣れへの第一歩
この曲から、同じ音が続く場合や明らかに前と同じ指使いで弾ける箇所には、指番号の表記が省かれていました。
初めて見たときは「え、ここはどうやって弾けばいいんだろう?」と一瞬戸惑いましたが、いざ練習を始めてみると、これまでの経験で自然に指が動くことに気づきました。
指使いがすべて書かれていると安心感はありますが、その分、楽譜を「見ればわかるもの」として頼りすぎてしまいがちです。
今回のようにあえて表記を減らすことで、自分で考えて判断する場面が増え、結果的に譜読み力や応用力が育っていくと感じました。
指番号が減るのは不安材料ではなく、「自分で読める力がついてきた証拠」。
そう思えるようになると、楽譜と向き合う姿勢も前向きになり、少しずつ“楽譜慣れ”への第一歩を踏み出せます。
同じ音は省略する工夫で自然に譜読み力を育てる
今回の楽譜では、同じ音が続く場合やパターンが明らかな箇所では、指番号が省略されていました。
最初は「書いてないと不安だな」と思いましたが、実際に弾いてみると、これまでの練習で身につけた指の動きが自然に出てきます。
こうした省略は、ただの手抜きではなく、自分で判断する習慣を育てるための工夫だと感じました。
書かれていないからこそ、音の並びやフレーズを見て「この指だな」と考える力が鍛えられます。
楽譜と向き合う時間が増えて指も頭も慣れてきた
指番号のヒントが減ると、どうしても楽譜をじっくり見る時間が増えます。
最初は少し面倒にも思えましたが、その分「譜読みする目」と「弾く指」が同時に鍛えられました。
特に、指が自然に音を追いかけられるようになると、演奏中の余裕が生まれます。
結果的に、以前よりも楽譜を怖がらなくなり、「見て考えて弾く」流れがスムーズになってきました。
まとめ|第3回レッスンの幕開けにふさわしい課題曲
「遠き山に日は落ちて」は、第3回レッスンの最初を飾るにふさわしい曲でした。
臨時記号や指使いの省略など、新しい要素がありながらも、これまでの基礎練習がしっかり活きる内容で、自分の成長を実感できます。
また、情感をこめる難しさにも触れ、「ただ弾ける」から「どう弾くか」へと意識を広げるきっかけになりました。
基礎力と表現力の両方に挑戦できるこの曲は、まさに第3回レッスンのスタートにぴったりな課題だったと思います。
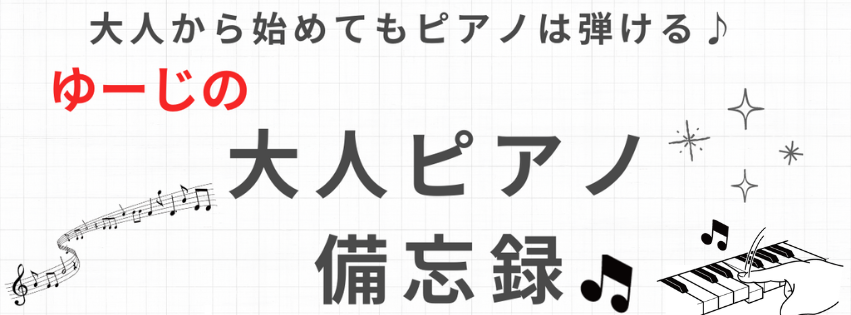
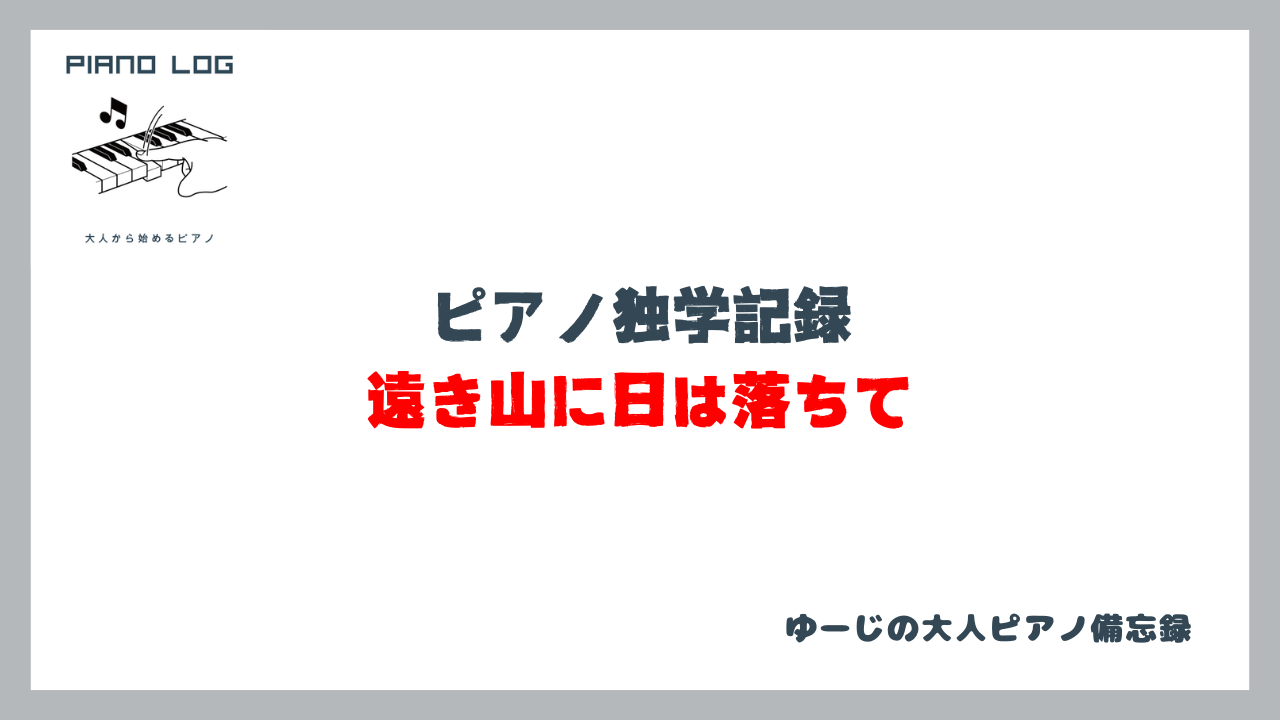


コメント